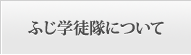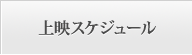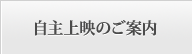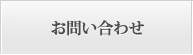6/18(火)琉球新報 ふじ学徒隊上映に寄せて - 野村岳也
野戦病院の2段ベッドは、うじ虫だらけの傷病兵でいっぱいだった。血と膿、そして排泄物の匂いが充満していた。16才の少女たちは、夢中でそんな患者の看護に当たった。脳症患者は訳の分からないことを口走り、壕内を徘徊する。手術室は、麻酔薬のない手術室で阿鼻叫喚の巷と化していた。灯火を持ったり、時に衛生兵と一緒に患者を押さえつけた。切断した手足を壕外へ捨てに行くのも学徒隊の仕事だった。その上、砲弾の下をかいくぐっての「メシアゲ」(食事運び)まさに生地獄の3カ月だったのだ。
日本軍は次第に南部一帯に追い詰められた。米軍は最後の掃討戦に入っていた。そんな一日、戦況の沈静化をみはからって、学徒解散の隊長命令が出る。重症患者の青酸カリ処理や、衛生兵の斬込隊への転属を命ぜざるを得なかった小池隊長は、兵隊でないこの子たちだけは、何としても救いたいとの悲願を持っていたにちがいない。「死んではならない。敵は民間人は殺さないから手をあげてここを出なさい。そして、家族のところへ帰るのだ」と諭し、最後まで一緒にと泣き叫ぶ学徒たちに「これは隊長命令である」と決然といいきった。学徒隊を送り出した後、隊長は青酸カリをあおって自決した。
あの狂気の戦争は終わった。学徒達は茫然と社会へ帰ってきた。そして、南部戦線へ出た多くの学徒隊の半数が戦死し、自分たちだけが奇跡的に助かったことを知るのである。
彼女たちの戦後がはじまる。戦後68年、それは長い長い苦悩と葛藤の道のりであった。はじめに生き残ったことが後ろめたく死者に恥る思いで何も語れなかったという。やがて、生かされたことの意味を考えるようになり、「どんなことがあっても、死んではならない」といった隊長の言葉がよみがえる。いつしか人を恋し、結婚し、子を産すに至った。そんな、ながい時間のなかで「ぬちどぅ宝」その言葉を痛感するのである。
しかし、彼女たちの戦場体験は子等に語られることはなかった。子供達の誰一人として母の戦場体験を聞いた者がいないことに、彼女たちの傷痕の深さをみるのである。孫が出来、その孫に対してはじめてあの体験を語りはじめる。私達は学徒隊の長く重い心の軌跡を多くの人々に知ってもらいたいと思っている。
映画「ふじ学徒隊」の沖縄一般上映は、桜坂劇場の今月15日からの2週間が最後となるだろう。この映画は、学徒隊の戦後を直接に描いてはいない。語る85歳の現在と語られる青春の記憶があるばかりである。
ふるさとの先輩の68年の半生と、その身になって考えてもらいたいと願っている。
(映画「ふじ学徒隊」監督)